
民間企業に就職するか、ポスドクになるか迷ってます……
博士課程修了後の進路は、大きく分けてアカデミアに残る(ポスドクになる)か、民間企業に就職するかの2つです。
この選択は一度決めると方向転換が難しいため、自分のキャリア目標・ライフスタイル・価値観を踏まえて慎重に判断する必要があります。
アカデミアのメリット・デメリット
【メリット】大学教授という社会的信頼
かつては「頭の良い子は医者か博士か」と言われ、医者と博士(大学教授)は社会的地位の高い職業として尊敬されてきました。
現在でも両者が「doctor」と呼ばれるように、その名残は色濃く残っています。
大学教授は、博士号の取得がほぼ必須条件であり、限られた人だけが就ける高度な専門職です。その社会的評価は非常に高く、ローン審査や結婚といった人生の節目においても信頼を得やすい傾向があります。
こうした背景から、「大学教授」という肩書きは、社会的信用という大きなメリットをもたらします。
【メリット】自分の研究テーマに打ち込める
企業では、研究テーマは経営判断で変わることが多く、成果や事業性が見込めなければ数年単位で変更されます。
一方、アカデミアでは自分がやりたいテーマを続けられるのが大きな魅力です。
例えお金にならないテーマでも、夢のようなテーマであったとしても、それが新しい学問の発見や社会への貢献につながる可能性があるのであれば、アカデミアでは研究する意義となります。
もし、専門分野を極めたい、独自のテーマを追求したい、などの思いがあれば、アカデミアへの進路が向いているのかもしれません。
【デメリット】ポスドクはアルバイト扱い
アカデミアの進路で最も注意したいこととして、入り口となるポスドクは実は正職員ではなく、任期付きのアルバイト扱いです。
月給30万が相場のため、中小企業に就職するよりも年収が高くなるように思えます。
しかしアルバイトのため、ボーナスはおろか、家賃補助や雇用保険、有給などの福利・厚生が一切ありません。
また、ポストが空かない限り、助教などの常勤職に昇進することもできません。

いつになればポスドクから昇進できるんだろう……
という不安は、年齢を重ねるごとに大きくなります。
長期的な生活設計を考える上で、この不安定さは大きなリスクになります。
【デメリット】研究室のトップになるまでは自由がない
アカデミアでは、研究室のトップは基本的に教授が務めます。
たとえ准教授や助教に昇進しても、教授が在任しているなど上の役職がいる場合には絶対服従がアカデミアの基本です。
稀に、40歳前後で教授に昇進したり、教授が退官して准教授がトップになるケースもありますが、非常に珍しい事例です。
一般的には50歳前後で教授になることが多く、それまでは自由に研究テーマを選べないと考えておくべきでしょう。
トップに就くまでは、学生の研究テーマに口を出す機会も限られ、学生指導、研究室運営、予算管理、論文投稿など、多岐にわたる雑務に追われます。
また、研究室のトップになるまでは、平日は深夜まで、土日も大学に出勤するのが当たり前の風土があります。
大学教員は裁量労働制のため残業代が支給されず、時間外労働が評価されにくいのも事実です。
有給休暇も付与されるものの、すべて消化できることはほとんどありません。
そのため、パートナーには仕事の実態をしっかり理解してもらい、協力や理解を得ることが不可欠です。
特に子育てや家事の分担をどうするかなど、早い段階から話し合いを重ねることが重要になります。

労働環境がいいとは言えない……
なお、昇進は学内の教授会で決定されるため、研究面だけでなく、人間関係の良好な維持も非常に重要です。
上下関係を軽視すると、昇進が遠のく可能性もあるため、注意が必要です。
研究室内はもちろん、学部内の教授とも良好な関係を築くコミュニケーション能力が必要になることも覚えておくと良いでしょう。
【デメリット】研究費は自分次第
アカデミアで研究を続けるためには、科研費などの研究資金を自ら獲得する必要があります。
そのため、自分の研究テーマの有望性をしっかりと示し、論文投稿や学会発表などで成果を積極的に発信しなければなりません。
また、学生の指導や育成も研究室運営の重要な一部です。
良くも悪くも、自分自身や研究室の成果が研究資金の獲得に直結するため、研究以外の業務にも責任感を持って取り組むことが求められます。
民間企業のメリット・デメリット
【メリット】ワークライフバランスが充実
民間企業の大きなメリットの一つは、給与に加え家賃補助や各種保険、資格取得支援、育児をはじめとする多彩な休暇など、福利・厚生が手厚いことです。
特に大企業の場合、これらの補助を含めると実質的な年収は表面上の給与の1.5~2倍に相当すると言われています。
さらに近年は、残業削減や全世代対象のハラスメント研修実施など、職場のストレス軽減に向けた取り組みが積極的に進められています。
加えて、初年度から15日以上の有給休暇が付与される企業も増加傾向にあり、ワークライフバランスを重視した社会人生活を送りやすくなっています。
【メリット】研究費の心配が少ない
大企業ほど研究費を多く確保できる傾向にあり、消耗品の購入や外部機関への試験委託など、効率的に研究を進める環境が整っています。
また、企業利益から一定の研究費が確保されているため、アカデミアのように「資金不足で試験ができない」といった心理的負担が少なく、安定した環境で研究に集中できるのも魅力です。
【デメリット】テーマは経営層が決定する
一方で、企業における研究の目的は利益創出にあります。
そのため、研究テーマは経営戦略や事業の成否に直結するかどうかが最重要視されます。アカデミアのように自由にやりたいテーマを追求することは基本的に難しいでしょう。
また、多くの企業では3~5年ごとに中長期経営計画を見直し、社会情勢や経営状況を踏まえて研究テーマの継続・中止が判断されます。
研究が上手く進んでいないテーマはもちろん、予定以上に進展しているテーマだったとしても、研究が中止になることも多々あります。

コロナの影響で研究テーマが一気に変わったってよく聞くよね
民間企業では、社会情勢や経営状況で研究テーマが変わることは理解しておいた方が良いでしょう。
【デメリット】研究職から離れることもある
本人も上司も「その業務が本当に適職かどうか」を完全に見極めることは難しく、多くの企業では人事ローテーション制度を導入し、社員に多様な経験を積ませる文化があります。
研究職であっても例外ではなく、博士号取得者であっても営業や事務職への異動が発生することがあります。
一度異動すると、数年間はその職種に専念する必要があるため、研究だけに集中したい人には合わない場合もあります。
しかし、最近では異動の希望を考慮する企業も増え、長期的には視野が広がる有益な経験となることも多いです。こうした点を踏まえ、民間企業では研究職から離れる可能性があることを理解しておくことが大切です。
道を変えることも可能
一度選んだ進路であっても、その道を生涯にわたって歩み続けなければならないわけではありません。
例えば、企業の研究職から大学教員へ転身する人もいれば、逆に大学教員から民間企業へキャリアを変える人も少なくありません。
もちろん、転職には一定の労力が伴い、新しい職場環境や業務内容に適応するため、多くのことを学ぶ必要があります。そのため、同じ分野で経験を積んできた人と比べると、スタート時点で遅れを感じることもあるでしょう。
しかし、キャリアの選択肢として転職の道が開かれていることを知っておくことは、将来の柔軟な進路選択につながります。
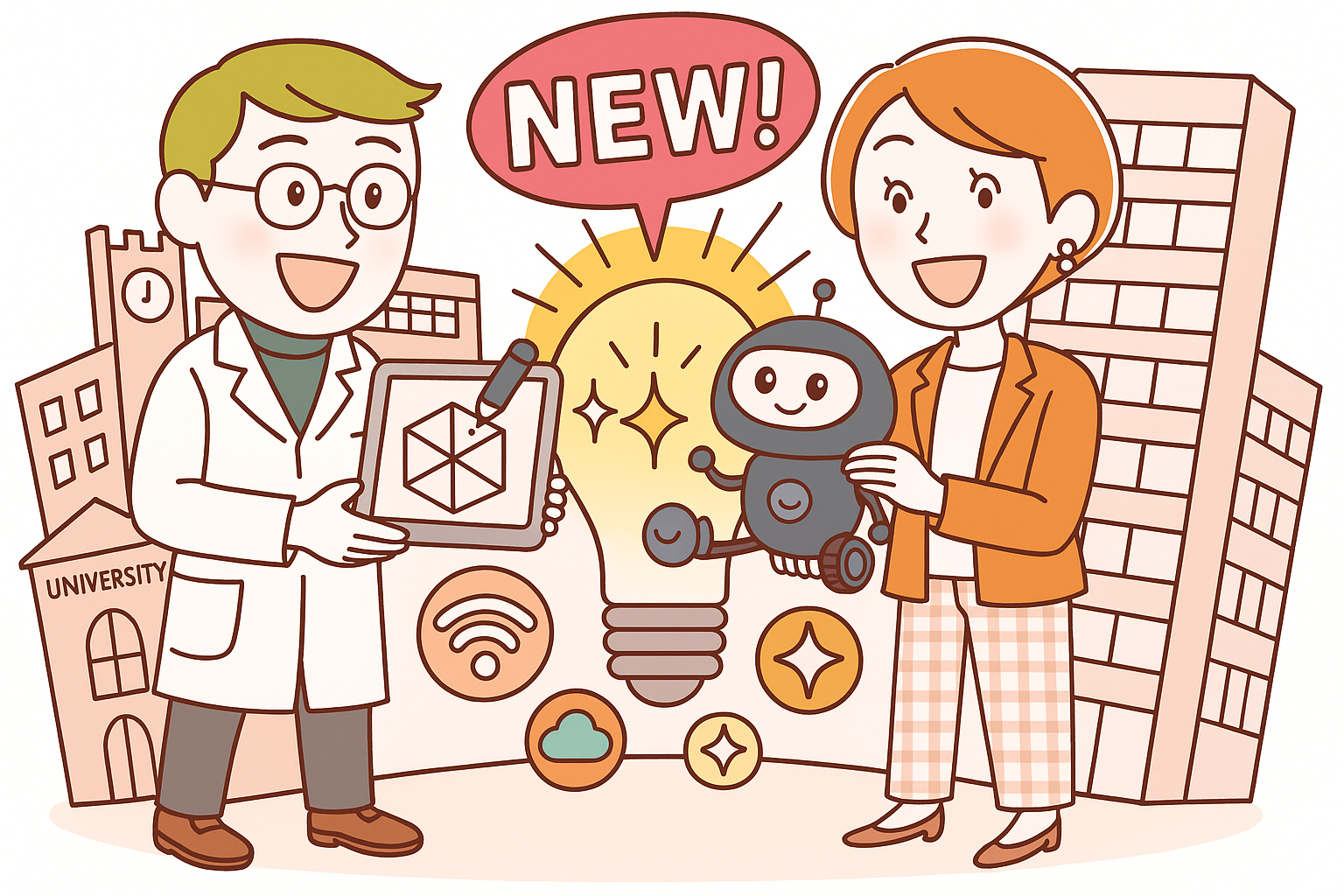


コメント