必ず構成を見直そう
研究概要の構成って意識していますか?
おそらく多くの就活生がほとんど意識していないのではないでしょうか?しかし、何万人の中から、人事が『聞いてみたい!』となる研究概要を作るには一工夫必要です。
もし、就活の研究概要を学会要旨の様に作成しているのであれば、このセクションで研究概要の作り方を見直してみましょう。
研究概要と要旨の違い

研究概要って、要は学会要旨でしょ?
と考えてる就活生は、漏れなくお祈りです。
では、就活における研究概要と学会などの要旨の構成にどのような違いがあるのか。理系の研究概要に多い2枚の時の構成だと以下のようになります。
要旨
- 背景・目的
- 方法
- 結果
- 参考文献
研究概要
- 背景・目的
- 課題と解決策
- 研究成果
- 研究の展望
- (参考文献)
- (研究業績)
赤字で強調しているように、研究概要と要旨の構成の大きな違いとして、研究の『問題点と解決策』・自身の研究成果から繋がる『研究の展望』が挙げられます。

課題・解決策って何!?
研究の展望とかいるの!?
研究概要で伝えるべき能力
では何故、この2つの項目が研究概要に必要なのでしょうか?
それは、そもそも大学の研究と企業の研究は目的が大きく異なるからです。
大学の研究では新たな発見と、学会や論文による発表(無利益)を目的としています。
一方で、企業の研究では消費者のニーズを捉え、この先何十年間とお金を生み出す特許(利益)を目的としています。
つまり、企業が就活生に求めるものは研究成果ではなく、研究の元となる問題点を考える力(企業研究における、消費者のニーズを考える力)と、研究結果から次の研究に繋げる力(企業研究における、研究成果を製品に繋げる力)です。
したがって、研究概要ではこれらの力をアピールすることが重要となります。

考える力があることをアピールするのが大事なんだね
研究概要で重要視されない内容
研究成果
企業がそこまで重要視していない内容として、研究成果が挙げられます。

え?研究成果が大事じゃないの?
勿論、研究成果があるに越したことはありません。
しかし、企業が知りたいのは企業に入って何ができるかです。大学でどんな成果を出したとしても、それは企業に入ってからは何の役にも立ちません。
それよりも、どんな実験手法を使ってきたか、どの分野を学んできたか、企業に入ってからも活用できる内容のほうが大事なのです。
ただし、面接を行うにあたり成果がないと議論をしにくいところもあるため、ある程度の成果を記載することは必要になってきます。
参考文献
学会要旨や論文だと必ず必要な参考文献ですが、研究概要についてはどちらでもよいです。
と言うのも、そもそも企業にとって学生が行ってきた研究内容はそこまで重要ではないため、参考文献まで読むことは滅多にありません。
勿論、書く余裕があるのであれば書いておいて損はないです。が、わずか2ページに多くのことを書く必要があるため、内容を削ってまで参考文献を入れることはお勧めしません。参考文献を入れるにしても1つか2つ程度に絞り、投稿者に自分が含まれているものを入れると良いでしょう。
研究業績
受賞経験などがある学生からしたら、是非とも入れたい項目。

学会で賞をもらったから、アピールしよっと!
勿論、受賞や科研費などは書いてもらえると企業としても評価はしやすいです。
ただし、何度も書きますが、企業としては大学時代の成果時代にはあまり興味はありません。受賞という成果に対し、いかに自分の能力をアピールできるかがポイントになります。
「本研究成果は○○学会で発表し、奨励賞を受賞した」
と書くよりも、
「この結果は□□と推察し、△△の追加実験で裏付けることで、○○学会での奨励賞受賞につながった」
のように、単に受賞した成果を主張するのではなく、自身の研究汎用能力が受賞につながったことをアピールできると良いでしょう。
また、上述した通り、研究概要は2枚程度の指定があるため、年度や開催地など、詳しく書く必要はありません。あくまで自分の研究内容を知ってもらう書類ということを忘れないようにしましょう。
研究成果が多い場合には主要なものを1件書き、「・・・他〇件」とすると、件数もしっかりアピールできるためおススメです。
なお、ESに研究業績の項目があったり、企業によっては3枚目に研究成果を書いてくださいという指定があったりするので、その場合は研究概要には書かないようにしましょう。

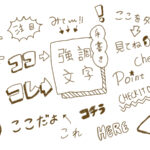
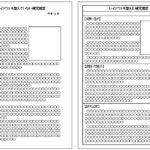
コメント